
この記事はこんな人にオススメ!
①子どもの不登校に悩んでいる。
②不登校から登校できるようになるまでの過程を具体的に知りたい!
③子どもの不登校の見通しがつかなくて不安な人
不登校って見通しがつきませんよね。
解決する未来が、これからどんな道筋をたどって子どもが元気になっていくのか、悩んでいるときは全く想像できない。
わかります。テルもそうでした。そして常に不安でした。
なので、そんな人のために、一つの例として、我が子が不登校になってから約二年間、どんなことがあり、どんな段階を踏み、学校に復帰していったのかがわかるように年表を作ってみました。
テルの体験を一つの例として、不登校に悩む皆さんのヒントにしていただけたらと思います。
ということで、見通しが全くつかなかった我が子の不登校開始以前から現在までの約二年間を具体的に時系列で大公開!!(記事は①と②に分けてあります)
年表を見る前に
テルの家の事情
まず年表を見るにあたって、テル一家のことをを少しばかりご紹介。

イライラMaxママ時代に長女が不登校になりさらにイライラがさらにパワーアップ。なのに、今ではそんなイライラをコントロールして「結果的には娘が不登校になってよかったかも」とまで考えられるようになった激変ママ。

小学校一年生の夏休み明けから学校に行けなくなる。二年経った現在(小学三年生)は勉強の遅れと極端な不安を理由に特別支援学級に通うことに。週明けは休むこともチラホラありつつ、「学校は楽しい」と言うようになり、母子登校すれば一人で授業を最後まで受けられるようになった。

長女より三歳年下。しっかり者であるが故に、長女のコンプレックスを刺激しがち。

教職関係のお仕事の人。何故だかよくわからないけどものすごく冷静。
年表を見るにあたって必要な心構え
子育てや不登校対応は家庭によって完全にオーダーメイドだとテルは思っています。
なので、テルの年表は参考にはなるかもしれませんが、同じことをしたら同じ結果になる保証はありません!
もしかしたら、テルほどの苦労と時間は必要はないかもしれないし、逆にもっと大変かもしれません。
その辺はお子さんとママをはじめとした家族の状況によって様々だと思うので、あまり真に受け過ぎないように気楽に見て下さい☆
年表の見方
☆当時の状況や感情をそのままリアルに書いてあるので、意味がわかりづらいかもしれません。
☆今回はあえて細かい解説はしません。
☆余裕がないときの記憶・時々書く三日坊主の日記・過去のスケジュールから年表を書き起こしているので、不自然な抜けがあるかもしれません。
☆娘は小学校低学年(一年生)で不登校になっています。不登校の理由は恐らく精神的な疲れによる不安だったのではないかと、今では思っています。
不登校年表 不登校前~不登校になってから学年が変わるまで
|
※テルのイライラなどの感情
|
|
|
※不登校に関する行動
|
|
|
※テルが気が付いたり、学んだこと
|
|
| 幼稚園 | 行き渋りで号泣するも、無理やりバスに乗せることもしばしば。 |
|
トイレ・お風呂・着替えなど、自分で出来ることをやって欲しがる。それにイライラして大きな声を出すことも。
|
|
| 長女本人もどうしてよいかわからないイライラがあるらしく、全てが思い通りにならないと泣いて叫んで大騒ぎがしばしば。 | |
|
育児疲れが酷い時期。子どもに泣かれると焦るし、騒がれるとイライラして物に八つ当たりする自分がいた。
|
|
| 4月 | 小学校入学 |
| 時々行き渋って休むことはあったけど、帰ってくると楽しそうに学校について話すことも多く、油断しまくり。 | |
| 5月 | 二者面談で担任の先生に学校ですごく泣いていると言われて寝耳に水。 |
|
学校に行きたくない、と言われると超イライラ。どうにかこうにか学校に行かせようとしていた。
|
|
|
登校直前に行くのを嫌がって登校班に迷惑をかけることにもイライラ。
|
|
| 夏休み | 時々学童に行きたがらない時もあったけれど、いつも通りの様子。 |
| 9月 | 始業式、登校したがらず、休む |
| 始業式翌日は登校。友達の隣の席になり楽しかったと言っていたし、先生も特に変わった様子はなかったと言っていた。 | |
|
さらに翌日ここから完全なる不登校がスタート。
|
|
|
「学校に行きたくない」が受け入れられず、朝はイライラMax。どうして? 理由があるの?と聞いても何もしゃべらない。
|
|
|
平日のパートを週末1日に変えてもらう。
|
|
|
夫や義両親にアドバイスをされるも、【行かなくちゃいけない学校に行っていない】状態が受け入れられず、逆にイライラ。
|
|
|
夫婦の話し合いで限界突破のテルブチギレ、号泣&過呼吸になる。
|
|
| ↑翌日、夫がわざわざ仕事を休んで私に子どもから離れる時間をくれる。実家に帰って、心の休憩と整理が出来た。 | |
|
長女習い事も行けなくなり、やめる。(元々休みがちだった)
|
|
| 10月 |
市営の教育センターのカウンセラーに週一ペースで話を聞いてもらうことに。(子どもより私の話を聞いてもらう感じでした)
|
|
学校とのやりとりは週に1回程度、電話のみ。学校に行けない状態は変わらず、話すことがなくちょっと戸惑う。
|
|
|
学童もやめる。
|
|
|
友達との交流を保てるように月一くらいで家に呼んで遊ぶようになる。
|
|
|
唯一一人になれる、トイレに寂しいと言ってついて来られて、やめて欲しくて怒鳴ってしまった。
|
|
|
どうにか勉強させようと、あれこれ工夫してやらせるが、間違いを指摘するとキレられ、勉強が終わる。お互いにイライラ。
|
|
| 12月 | 子育てに関して学ぼうとする余裕が少し出て、youtubeやネットを見始める。 |
|
自分が過保護だったと気が付く。なんでもダメダメ言い過ぎで全然子どもの自由にやらせていなかった。
|
|
|
子どもは自身が困る体験で成長する、ということにはじめて気が付き、その機会を奪っていたことに気が付く。
|
|
|
「~しないと~するよ!」という脅迫のような交換条件が子どもに悪影響だと知る。
|
|
| 長女が親の顔色を見て一人でトイレに行くことなどを頑張っていることを知る。 | |
|
寝る前のトイレは面倒だから一緒に来て全部やってと言われ、「その面倒を私にかけるのか!?」と怒ってしまう。
|
|
|
やってあげられることは選択肢を与えてあげるのはよいが、絶対にやってほしいことは「~しなさい」と言うべきと教えられる。
|
|
|
長女に抱っこをやたらとねだられる。なるべくした方がよいと知る
|
|
| 未だに間違いを指摘するとキレられるのは変わらず。 | |
| 少しずつどうして自分が学校に行きたくないのかを考えて答えられるようになってきた | |
| 遊びでも負けると号泣。人に合わせて楽しく遊ぶことが出来ない様子。 | |
|
大したことない怪我に絆創膏を貼りたがるのに無性にイライラ。もったいないが通用しない。寄り添ってあげられなかったと反省。
|
|
|
子どもの気持ちに共感してあげることが大切だと知る。
|
|
|
失敗されたり面倒なことを、先回りせずにチャレンジ回数を増やしてあげようと思い始める。
|
|
|
ダメなところを叱るから、出来たことを褒める方向で自己肯定感を上げた方が良いと知る。けど褒めるとこが中々思いつかない…。
|
|
|
ダメなことは頭ごなしにダメと言うのではなく、どうしてダメなのか理由も言った方がよいと知る。
|
|
|
長女は憧れているキャラクターになりきると普段できないことが出来ると気が付く。いつもの自分には自信がない?
|
|
|
子どものやる気は体と心が整っていないと出てこないことを知る(次女はすぐやる気になるが、姉はなかなかならない)
|
|
| 1月 |
年始から教育センターに行けなくなる。久しぶりだから行きたくないと言い出し、何回か休む
|
|
通学路を歩く練習を少しずつ始める。
|
|
|
校門の前まで行けるようになる。
|
|
| 週末しか働けず、お金が稼げないことに関する罪悪感があったが、家族にとって優先すべきこと何だとパパに諭され、気にしないようになる。 | |
|
放課後、担任の先生と校舎の外で会うことに成功。私に抱き着いて一切離れす。会話出来ず。
|
|
|
放課後の先生訪問二回目。妹がいたおかげで何故か緊張せず、先生と二人きりで話すことにも成功する
|
|
|
放課後先生訪問3回目。先生と校舎の中に入って歩くことに成功。
|
|
| 2月 |
放課後の先生訪問4回目。教室に入って自分の席で先生と話すことができた。
|
|
放課後の先生訪問。逆上がりの練習がしたいと言い、先生に付き合ってもらう。
|
|
|
みんなが授業している時間に学校に行って教室で過ごさせてもらい始める(週一行くか行かないか)
|
|
|
何度か教室に入って授業を受けることが出来たが、数日で出来なくなる。
|
|
| クラスの懇談会で、他の生徒の成長の話を聞き、置いて行かれている気持ちになり、私がめっちゃ泣きそうになる。 | |
| 3月 |
一日1時間くらい別室登校で、教室で少しだけ勉強をするようになる。
|
不登校前半戦はイライラとの格闘&子育てを学ぶ時間
ご覧の通り、テルは長女が不登校になる前から子育てのイライラが半端なかったです。
これはテルの場合、完璧主義の弊害だったり、子どもの気持ちを理解する能力が低かったりが原因だったんですが、心に余裕がないからイライラ解決の糸口が見つからず、そんな自分自身にかなり落ち込んだりしていまいた。
また、少し不登校に慣れてくると、解決しようと躍起になって様々な情報を得ようとしました。中でも専門のカウンセラー(市営教育センター)さんにピンポイントでもらえるアドバイスはとても有難かったです。まぁ、知識がついたところですぐに思い通りに行動できるわけではありませんし、行動できてもすぐに効果があったわけではなかったんですが。
ただ、焦らず時間をかけて子どもと自分自身と向き合った結果、テル家は長女の不登校以前より現在の方が確実によい家庭になりました! その辺りの体験談は違う記事で紹介出来たらと思います。
不登校年表の後半も公開しているので、そちらもチェックしてみてください!

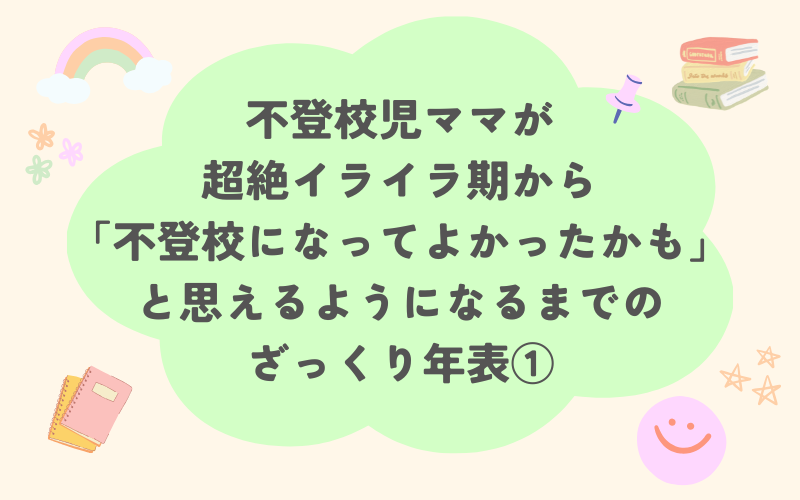



コメント